麻雀の基本
麻雀は一般的に4人でやる。3人でも遊べるがルールが少し異なる。
14牌(3×4+2)で役を作り、和了(あがり)を目指す。
点棒を奪い合って最終的な点数を競う。
初めに13牌配られ、その後、一牌ひき、一牌捨てる。その繰り返しで手牌の形を作る。
あがりかたは、自分でひいた牌であがるツモと、相手の捨て牌であがるロンがある。
親1人と子3人でプレイし、親は持ちまわり制。
一ゲームは、東一局〜四局まで、南一局〜四局までの半荘(はんちゃん)。おおざっぱに言えば、二回づつ親が回ってきたら終わり。ただし親のときあがると親を続けられます。親を続ければ続けた回数だけボーナスがつきます。 更に、親のときにあがると点数が1.5倍になるのでお徳! 親のときは頑張りましょう!
東場(東一局〜四局まで)では東が、南場(南一局〜四局まで)では南が、全員の役牌(後述)となり、その他、東南西北、該当する字牌がその局、自分の役牌となります。
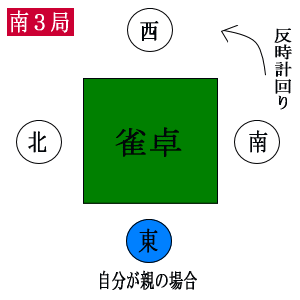
南3局で自分が親の場合は、南と東、白發中が役牌になります。
牌の種類
数牌と字牌の二種類。
数牌  萬子(まんず) 萬子(まんず) 筒子(ぴんず) 筒子(ぴんず)  索子(そうず)の1〜9まで、各4枚。 索子(そうず)の1〜9まで、各4枚。
字牌        各4枚。 各4枚。
字牌の呼び方は とんなんしゃーぺーはくはつちゅん
麻雀の手牌
基本は4面子+1雀頭の14牌。
面子はひとつのグループで、その構成は3種類。
     
刻子(こーつ) 同牌同種3枚
     
順子(しゅんつ) 連番同種3枚
   
槓子(かんつ) 同牌同種4枚
   
雀頭(じゃんとう) 同牌同種2枚
4面子(3牌×4グループ)+1雀頭(2牌×1グループ)=14牌
という計算になっております。以下は一例。
             
鳴く
相手の捨て牌をもらって面子をつくること。あがりは早くなりますが、飜が下がります。そして鳴いた場合は、その牌を他の人に見せなければならない。「鳴いてもあがれる役」を覚えるまでは鳴かない方が吉。種類は3つ。
チー
自分の手配2枚と捨てられた牌1枚で順子をつくる。ただし自分の左隣の人からしかできない。
ポン
自分の手配2枚と捨てられた牌1枚で刻子をつくる。誰からでもオッケー。
カン
自分の同種同牌4枚で宣言する「暗カン」と、誰かの捨て牌1枚と己の手配3枚で作る「明カン」がある。感覚的にはポンみたいな感じですが、とりあえずは複雑なので、チーとポンだけ覚えておいてください。
役
ある決まった手牌の形の事。難しい役を作るほど高い点数がもらえます。役のレベルを飜(はん)と呼ぶのですが、飜がひとつもない形だとあがれません。複数の役を組み合わせることでどんどん高得点が狙えます。
ほんっとうにたくさんあってこれを覚えるのが難しいのですが、基本はリーチ、ピンフ、タンヤオ、ファンパイの四つを覚えておけばOK。
もっと詳しく知りたい場合は、こちらを参照してください。
リーチ(一飜)
門前(一度も鳴いてない状態)、あと一枚で和了できる! という時に千点を支払い宣言する。しかし、一度宣言したら基本的に手の変更は出来ないので注意。
初心者はとりあえずリーチ! いちばん解りやすい役です。
ピンフ(一飜)
門前(一度も鳴いてない状態)、4順子+1雀頭を集める。ただし最後は両面待ちであがる。雀頭は役牌(後で説明します)以外であること。
             この状態で この状態で  待ち (一例) 待ち (一例)
タンヤオ(一飜)
1、9、字牌を使わない役のこと。1、9、字牌をヤオチュウハイを言うのですが、それを断つから、断ヤオ。鳴いてもOKかNGは参加者で決めます。
              (一例) (一例)
ファンパイ(一飜)
いわゆる部分役で、役牌を3枚(あるいは4枚)集めます。鳴いてもOK。
役牌は、白、發、中。
そして東、南、西、北は、人によって役牌になったりならなかったりする。役牌となるのは、場風(東3局だったら、場風は東)の牌と、自風(自分が西だったら、西を自風と言います)の牌です。
この役は鳴いても一飜つくので、とても簡単で手っ取り早いです。親のときなどとにかく早くあがりたいときにオススメ。
ドラ
面子や雀頭にしたら持っている数だけ飜が増えるボーナスのような牌。ただしドラだけあっても役がないとあがれないので注意!
局の最初にドラ表示牌がめくられ、その牌の次の牌がドラになります。
表示牌  ドラ ドラ  表示牌 表示牌  ドラ ドラ 
字牌の場合は 東南西北 と 白發中 というくくりになってます。
参考にさせていただきました : 麻雀のま
戻る
|