※ ここでは作中の専門用語の解説などをしています。
説明文はこちらを参考にさせていただきました。もっと詳しく知りたい場合は是非!
麻雀の手牌
基本は4面子+1雀頭
面子っていうのはひとつのグループで、その構成は3種類。
     
刻子(こーつ) 同牌同種3枚
     
順子(じゅんこ! ではなくしゅんつ) 連番同種3枚
   
槓子(かんつ) 同牌同種4枚
   
雀頭(じゃんとう) 同牌同種2枚
4面子(3牌×4グループ)+1雀頭(2牌×1グループ)=14牌
という計算になっておりますです。以下は一例。
             
牌の種類
 萬子(まんず) 萬子(まんず) 筒子(ぴんず) 筒子(ぴんず)  索子(そうず)の1〜9までの数牌4枚づつ。 索子(そうず)の1〜9までの数牌4枚づつ。
そして       の字牌4枚づつがあります。 の字牌4枚づつがあります。
字牌の呼び方は とんなんしゃーぺーはくはつちゅん 。
りんぴょうとうしゃかいじんれつざいぜん! みたいで繋げて言えるとかっこよいです。
短編「雀荘にて雨時々、あいのむち」の主人公の名前はまんま索子とかいて、そうこだったのですが、その他にも八幡さんは「はちまん」。ピンさんも筒子(ぴんず)から名前を頂きました。
ちなみに雀荘「千鳥」の座りは上から見てこんな感じ。
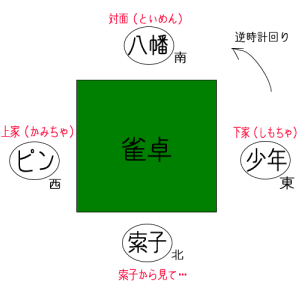
鳴く
相手の捨て牌をもらって面子をつくること。あがりは早くなりますが、翻がひとつ下がります。種類は3つ。
チー
自分の手配2枚と捨てられた牌1枚で順子をつくる。ただし自分の左隣の人からしかできない。
ポン
自分の手配2枚と捨てられた牌1枚で刻子をつくる。誰からでもオッケー。
カン
自分の同種同牌4枚で宣言する「暗カン」と、誰かの捨て牌1枚と己の手配3枚で作る「明カン」がある。
ドラ
面子や雀頭にしたら持っている数だけ翻が増えるボーナスのような牌。
局の最初にドラ表示牌がめくられ、その牌の次の牌がドラになります。
表示牌  ドラ ドラ  表示牌 表示牌  ドラ ドラ 
字牌の場合は 東南西北 と 白發中 というくくりになってます。
聴牌(てんぱい)
あがるのに必要な牌があと1枚の状態をさします。後2枚なら1向聴(いーしゃんてん)、3枚なら2向聴(りゃんしゃんてん)と増えていきます。
リーチ
役の一つ。門前(一度も鳴いてない状態)、聴牌で、千点棒を支払い宣言する。しかし、一度宣言したら基本的に手の変更は出来ないので注意。
ロン
相手の捨てた牌であがること。点数は捨てた相手から全部頂きます。
面断平三色ドラ二 の 親跳
役の名前がくっついてます。以下は一例。
             和了牌 和了牌  ドラ ドラ 
面前(鳴かずにあがる 1翻)
断ヤオ(1、9、字牌なし 1翻)
平和(4順子+1雀頭 ただし、最後は両面待ちであがる 1翻)
三色(三種同順子 2翻)
ドラ(もっている数だけ翻がプラスされる ただしドラだけだと役にはならない)
計・7翻 6翻以上は跳満と呼ばれ、12000点がもらえる。ただし、親のときは×1.5なので18000点。
染め手
数牌の柄を1つにしぼった役。混一 や 清一 があります。
染め手を狙っている場合、必然的に捨て牌が偏るので見破られやすいです。
鳴き三色、チャンタ、河底撈魚、ドラ一
              和了牌 和了牌 ドラ ドラ 
三色(三種同順子 2翻、鳴いているので−1翻)
チャンタ(1・9・字牌のみ 2翻 鳴き−1翻)
河底撈魚(最後の牌でロンする 1翻)
ドラ(この場合は1索)
=4翻
戻る
|