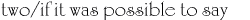
「……き……夏生?」
囁くような声に意識を戻すと、心配そうな由紀の視線とかちあった。
夏生が手にしていた青りんごチューハイの氷は溶けきっていて、汗をかいたグラスは手を濡らす。
ぽたり、とたれてしまった雫が灰色のスカートに暗い染みを残した。それがまるで涙のようだと、夏生は錯覚する。
酒の臭気がかすかに混じる居酒屋では、皆は好き勝手に分かれて喋っている。どこか浮ついた雰囲気が漂っている中で、自分という存在が激しく異質だった。
由紀は自分が連れてきたからという責任感からか、夏生の隣に付きっぱなしで、夏生が自分の事は気にせずに楽しんできて、と言っても頑として譲ろうとしない。
それは被害妄想だったのかもしれないが、時々周りからの視線が、由紀を独占している事に対しての不満を含んでいるような気がして、夏生は余計に萎縮した。次第にマイナスへと走る思考がとめられない。由紀が幾度か皆の所へ行こうと誘ってくれたが、こんな心持ちのままでは、不自然な笑顔と態度で楽しげな雰囲気をぶち壊してしまうだろうことは知れている。
そっと肩に置かれた手を辿って、夏生は由紀を見つめた。
笑みを浮かべよ。という神経の伝言ゲームはどこかで失敗し、夏生の唇の端はかすかにひくりと不恰好に攣った。由紀ははっきりと表情を曇らせる。
「――やっぱり無理矢理誘っちゃったみたいだね」
「あ、違うの。――ちょっと、調子が悪くて……ごめん」
俯きがちになっていた顔を上げて否定したが、覇気の無い言葉には説得力が欠けていた。
「全然大丈夫じゃないじゃない! そだ、友達に車で送らせる」
「大丈夫。一人で帰れるよ……子供じゃ、ないんだから」
「駄目よ! 病人は黙ってなさい。――ちょっと田巻!」
由紀は夏生の喋っている途中で言葉を遮って、他の場所で話していたグループの一人に声をかける。明るめに脱色された茶色の頭がゆっくりとこちらを向いた。
「ん――あぁ? なんだよ曽根川。今盛り上がってる所なんだけど……って田辺さんどうかしたの?」
文句を言いながらもこちらにやってきたのは、夏生たちと一緒の講義をとっている田巻透(たまきとおる)だった。由紀とも仲が良いらしく、講義があるたびに話しかけてきたから、夏生も自然と顔と名前を覚えられた人物である。透は由紀と同じくお祭り好きで、宴会といった類は好きだと言っていたから、今日も例に漏れず参加していたらしい。
透は夏生の存在に気付くと、続けようとした言葉を引っ込めて、長身をかがみこんだ。ふわりと柔らかめの髪の毛がゆれる。由紀は呼びつけたことへの謝罪はすっ飛ばし、用件から切り出した。
「アンタ今日車でしょ? 飲んでないみたいだし、夏生を家まで送ってくれない?」
突然の要請に透は驚いたようだったが、その黒目を細めてわざとらしく下品に笑った。
「勿論いいですけどぉ? でも送り狼にならない保証はねぇよ? ゲッヘッへ」
「――馬鹿なこと言ってると殴るわよ。夏生、具合悪いんだから」
「うっそ、マジで? ごめんな田辺さん、大丈夫?」
由紀が嗜めると、透はふいにふざけた表情を取っ払って、夏生を心配そうに覗き込む。
透にまで心配されるのが心苦しくて、大丈夫だからと言ったけれど、透は聞いているのかいないのか「即効で車とって来るから」と立ち上がった。
家まで付いてくる、と言って聞かなかった由紀を何とか説得して居酒屋に残らせると、夏生は会費を払ってから透の車に乗り込む。由紀は会費はいらないと言ったが、そういうわけにも行かず、押し付けるようにしてお金を握らせた。
助手席に乗り込んでからシートベルトを締める。夏生が遠慮がちに住所を告げると、透は軽く頷いてからアクセルを踏んだ。
透の運転は、意外と言っては何だけど、思いのほか安全運転だった。
夏生は免許証を持っていなかったからわからなかったが、ちゃんと信号のところで左右確認してからスムーズに発進している。普段はよく喋る人なのに、車の中では沈黙している透に夏生は正直な所ほっとした。もしかしたら気分が悪いという夏生を気遣ってくれたのかもしれない。
「田辺さん、着いたよ」
少しうつらうつらしていたら、思いもよらないほど近くで低い声が聞こえた。
跳ね起きた夏生に透は一瞬目を丸くすると、「そんなに俺の運転心地よかった?」とからかうような笑みを浮かべた。それが妙に恥ずかしかったが、夏生はお礼を言ってしまおうと顔を上げる。
ありがとう、と。
口に出す瞬間。息が詰まった。
あの声が聞こえ、夏生は陸に上がった人魚のように言葉を失う。
生々しく鮮やかに蘇った声は夏生の心に新しい引っ掻き傷をつくった。
「――田辺さん、ほんとに大丈夫? 顔色悪いよ?」
急に凍りついたように黙り込んだ夏生に透はそっと声をかけた。
夏生は消えそうな声で「送ってくれて、ありがとう」と言った。その態度は透を困惑させたみたいだったが、体調が本当に悪いのだと誤解してくれたようだった。
お大事にと、透の言葉を背中に受けながら、アパートのエントランスへと足を向ける。透に手を振る余裕も夏生には無かった。
去っていく車の音を耳にしながらも、透の車を見送らなかったのは失礼だったかもしれないと少し後悔した。しかし夏生はあれ以上は人と一緒にいるのが苦痛だった。ぽろぽろと心の塗装が剥がれていくみたいにコントロールは失われる。
夏生はかがみこんだ膝に顔をうずめた。涙は一滴も出てはこなかった。
ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。
その言葉を咀嚼でもするように心の中で呟く。
――何故言えなかったのだろう、そのたったの五文字が。
あの瞳に射られ、声を聞いた瞬間、夏生の心は囚われたのだ――あの冷たい蒼の海へ。
無色透明な世界に、鮮烈な色を与えてくれたひと。
同時に痛みを与えてくれたそのひとの、孤独を夏生はまだ知らない。
 
|