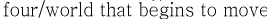
夏生は朔を見つめている。
もしこの瞳に穴を開ける能力があるとすれば、朔の体はとっくの昔に蜂の巣だ。見る、という行為をこんなに能動的におこなったのは初めてだった。
見つめている度に、増えていく小さな発見。
例えばそれは、下を向くたびにずれる眼鏡を上げる動作だったり。なにか間違いを書いた時に、いらいらと舌打ちする音だったり。睦月朔、とレッテルの貼られたそれは大切に、積み上げられていくのだ。――それはお世辞にも褒められた趣味でもなかったのは確かだけれど。
彼は、驚くほど無口だった。
どんなに夏生が耳を澄ましていたとしても、その閉ざされた口から無駄に言葉が飛び出す事は無い。このゼミには仲の良い友達はいないのか、彼はいつも一人でいた。だから友人と話している所を見たこともないし、必然と彼の声を聞くことが叶うのは出席を取る時の返事のみ。それが夏生には大いに残念だった。――少なすぎる。
まるで縫いとめられたかのように閉じられた唇。一度しか向けられた事の無い鋭い眼差しは、やはり今日も手元のキャンパス地のノートに向けられている。文字を書きとめていく指を見ながらも夏生は、あの人の手は冷たそうだと思った。
手の冷たい人は心が暖かいというジンクスを思い出す。
もし彼の手が冷たいとして、もしそのジンクスが正しいとしたら、それは多分どちらかが嘘っぱちなんだろう。あの声をしているあのひとの瞳は凍てついていたのだから。
「今日は、ここまでにしましょう」
にこにこと人の良さそうな笑みを浮かべた中谷教授が、夏生の意味の無いパラドックスを中断させた。
由紀の意地悪な視線に気付かない振りをして、夏生はノートを鞄に詰めていく。最近はずっと朔を見つめていた夏生に聡い由紀が気付かないはずも無く、その話題で夏生をからかうのが彼女のお気に入りだった。
「夏生ー? これからどうする? 暇なら駅前の新しく出来たケーキ屋さんよってかない?」
「ごめん。ちょっと教授に聞く事があって。また明日とかじゃ駄目?」
その誘いは凄く魅力的だったけれど、単位取得のために必要なレポートはその甘い誘惑を断ち切る力を充分に持っていた。
渋々頷いた由紀に謝りながらも、夏生は柔らかく笑った。それも夏生と一緒にすごしたいという彼女なりの我侭なのだから憎めないのだ。由紀の若草色のカーディガンの背中に手を振って見送ってから、夏生はレポートを片手に廊下を歩き出した。
大学の廊下は何時も薄暗い。蛍光灯の数が足りないのか、ワット数が少ないのか、夏生はよくわからなかったが、夜などに来ようとは絶対に思えない陰気さがある。そうとうな年月が経っているのと経済的な理由もあるのかもしれない。
夏生はC塔の端部屋を目指していた。その部屋の主である中谷教授は古典文学を専門として、柔和な瓜実顔がいかにもな人物だ。その世界ではかなり有名らしく、まれに解説書などに名前を見ることもあった。
とんとん、と軽くノックをすると入室を促す声が聞えてくる。失礼します。と断ってから、夏生はドアを開けた。
「良くかけてるよ田辺さん。あとは全体的にもうちょっと論点を絞ったほうがいい」
「はい、有難うございました」
穏やかに微笑みながら褒めてくれた教授につられて、緊張して張り詰めていた頬が緩んだ。自分でもこつこつ書いてきたレポートだったから自信もあった。はっとする独創性や突飛さは無かったけど、事実にもとづく解釈などをまとめた手堅いレポートには仕上がっていたはずだ。
――軽いノックが聞こえ一人の人物の来訪を控えめに告げる。
どうぞ。と言った教授に答えるようにキィとドアが金属的な音で鳴いた。その入ってきた人物を認めたとき、夏生の心臓は軽く鼓動をとめた気がした。――睦月朔だ。
朔は夏生を一瞥したが、それは直ぐに逸らされた。夏生に話しかけたことがあるのにも、夏生が同じ講義を取っている事にも気付いた様子はない。――いや、もしかしたら彼には取るに足らないこと過ぎて、忘れてしまったのかもしれない。そう思うと何かが抜け落ちたような喪失感を感じる。
「ああ、睦月君。君もレポートかな? 御免ね、もうちょっと待ってくれるかい?」
教授は夏生にレポートを返しながら、朔にその柔らかい笑顔を向けた。
「いえ。これを提出しようと思っただけです」
朔は手にしていたレポートを教授の机の上に置くと失礼しますと、軽く頭を下げた。夏生は彼の声に酔ったような夢心地で、朔が部屋の扉を閉めてからも少しの間はぼんやりとしていた。
そして唐突な教授の声に、危うく自分のレポートを落っことしてしまう所だった。教授は夏生を呼んだわけではなく、ああ、しまったとか何とか言いながら、朔の出て行った扉と手元に持っていた別のレポートを見比べていた。どうしたのかと夏生は成るべくさり気無さを装いながら聞く。
「あぁ、睦月君――今入ってきた子だけど、彼の先学期のレポートまた返しそびれてね。別に、急ぐわけでもなさそうなんだが、早いに越した事は無いだろうから」
教授は困ったように頭をかいていたが、結局、次の機会にしようとそのレポートを机の上に戻した。その紙の束を見つめていた夏生の頭の中にぱっと何かが閃いた。何故その時、そんな考えが浮かんでしまったのか、後になっても理解できない。――そう、多分その時が普通でなかったのだ。
高揚からか、緊張からか少しつっかえそうになりそうな言葉を、夏生は衝動的に口に出していた。
「――あの、教授」
色が世界を、ゆっくりと動かし始めた。
 
|