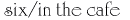
次の日の夏生の目覚めは良く言って「どんぞこ」悪く言って「生まれてきたことを後悔します」まさにそんな気分だった。
あの冷たい瞳の呪縛から解かれた後、夏生は自分がどうやって家まで戻ってきたのかはっきりと覚えていない。自分が夕食を食べる事が出来なかったのはぼんやりと思い出したが、一晩経った今でも食欲なんて湧いてこないし、それどころか逆に吐き気まで覚える。夏生はやんわりと労うように胃のあたりを撫でた。
枕元に置いてあるアラーム時計はセットした時間より30分は早い所を指している。これ以上寝ることも出来ないと判断した夏生は体を起こして、大学祝いにと父に買ってもらったドレッサーの鏡を覗き込んだ。そしてそこに写った自分の隈の酷さにますます落ち込む。
一瞬大学を休もうか、という考えが頭を過ぎったが、そういえば講義の後に由紀と新しいケーキ屋さんに寄ろうと約束をしていたのだ。具合が悪いと言えば由紀も納得してくれるだろうけれど、嘘を吐くのは忍びないし、必要以上に心配をかけるのも申し訳ない。こんな酷い顔を見せるのにも抵抗はあったけれど、コンシーラーで多少は隠せるだろうし、しきりに寝不足だったのだと言い切れば、無理矢理聞き出されることも無いだろう。
夏生は女であった事に感謝をしながら、いつもより少しだけ念入りに眼の下に化粧を施した。
「夏生! お早う――ってあんたどうしたの、酷い隈」
「ちょっと寝不足なの」
目ざとい由紀に出会い頭に見咎められて、夏生は用意しておいた言い訳を即座に口に出した。その不自然な声の硬さに何かを察したのか、深くは追求せずにあ、そうと、由紀は流してくる。
課題をやってきたのか、という由紀の問いに情けない顔で首を横に振ると、珍しいわねと言いながらも、ノートを見せてくれた。
何も説明しないのを悪いとは思いながらも、夏生は詮索しない由紀の思いやりに甘えることにした。
講義が終わると、由紀はトートバックの中にノートを手早く片付けてから、夏生の腕に腕を絡めた。
「今日こそはケーキ屋行くわよ!」
「うん、喜んで」
由紀のテンションの高さにまだぎこちなく笑いながらも、その元気のよさに夏生は救われた気がした。
すると由紀は首だけ後ろを向いて顎で講義室の入り口のほうをすい、と指し示した。それにつられて夏生がそっちに視線を移すと、見たことの在る人物が片手を上げてひらひらと振っているのが目に入る。由紀は綺麗にカーブを描いた眉をほんの少しだけ歪ませて呆れた風に付け足した。
「今日はお邪魔虫が是非お供したいって、ね」
新しく駅前のビル二階に出来たケーキ屋は流石にたくさんの人で賑わっていた。そこは外側が総ガラス張りで、お茶をしながら外の町並みが見下ろせるという洒落たつくりになっている。落ち着いているが明るめの照明が使われた店内には、透明でなだらかな円を描いたガラスケースの中にまるで美術品のようにケーキが陳列されていた。まるで宝石のようなケーキたちはフランス帰りのパティシエが作っているもので、それも口コミの人気に拍車をかけているらしい。――総て情報通の由紀の受け売りである。
夏生たちはやっと木を基調とした洒落た四人がけのテーブルに腰を落ち着けた。
「このケーキマジ美味い! 田辺さんのもちょっと味見していい?」
夏生は唐突な台詞に戸惑いながらも、自分のショートケーキが乗った皿を透の方に近づける。透は子供のように瞳を輝かせると、遠慮なくフォークを突き刺し、大き目の一口を口に運ぶ。そしてこれ以上の幸せは無いと、表情をだらしなく緩めた。ほっぺたが落ちている顔ってこんなのかもしれない、と夏生は思いながら、自分のショートケーキをなんとなくこっそりと引き寄せた。
そんな透の表情に由紀は心底呆れた様子で、食べかけのモンブランから手を離して、頬杖を付いた手の先でフォークを弄んでいる。
「田巻、酷く間抜けな顔になってるわよ――って素だからしょうがないか」
「何とでも言え曽根川。甘いもの食べてる時の俺はすげぇ寛大だってことに感謝するがいい」
「誰が連れてきてやったと思ってんの? 一人で来る勇気がなかった、ただのへたれの癖して偉そうに」
「入っちまえばこっちのもんだ。でかい顔はさせねぇよぉだ!」
頬張りながら透は鼻を鳴らした。食べるのに集中しながらもしっかりと言い返せるなんて器用だなと夏生は変な所で感心する。由紀も透との口喧嘩は慣れているのだろう決して負けていない。
「あ、そう。これから二度と誘ってあげないから」
「スミマセン曽根川様、どうか誘ってやってくださいませ」
ぽんぽんと目の前で交わされる息の合った漫才のような言葉についつい笑ってしまう。そんな夏生の様子に気付いて、透は二皿目に突入していた自分のチョコレートケーキを差し出した。
「田辺さんも、もし良かったらどう? このこってりとしたビターチョコレートのコーティングがふわふわなパウンドとマッチしててマジ絶品だから!」
「あんたは評論家かい」
すかさず由紀に突っ込みを入れられていたが、透の力説と勢いになんとなく押されて夏生は頷いた。
嬉しそうに勧めてくる透のケーキの端っこ少しだけを頂いてお礼を言うと、もっといっぱい食べてよ。と不満そうな透。夏生が困惑すると、由紀に「強制しないの!」とたしなめられて透はすぐに口をつぐんだ。
口にしてみると思っていたよりも甘くないビターチョコレートが舌の上で上品に溶けていく。それに対してパウンドは甘めで、その後にダージリンを含んだ後の甘みが丁度いい。
美味しい。と夏生が素直な感想を漏らすと、透は自分が褒められたかのように胸を張った。
「よかった夏生が笑ってくれて。あんたほんとに酷い顔してたんだもん」
ほっと安心するように由紀は息をつく。その口調からは本当に心配していたという事が解って、夏生は俯きながらごめんと呟いた。
「べっつに、謝ってくれなんて言ってないけど。で、何? あの睦月朔と何かあったとか?」
「ゆ、由紀!」
夏生は唐突に朔の名前を出した由紀に慌てながら透を横目で見たが、透は少し気まずそうに目線を泳がせて「ゴメン、実は知ってた」と小さな声で言った。思わず夏生は由紀に怨めしそうな視線をおくる。
「ちょっと誤解! 私は言ってないわよ!」
胸の前で掌をぶんぶんと振って由紀は弁解する。引き継ぐ用に、透は口の中のものを飲み込んでから喋りだした。
「ん、曽根川から聞いたんじゃなくって。あんなに熱い視線送ってたら、誰でも気付くっしょ」
そんなに皆に気付かれるほどばればれな視線を送っていたのだろうか。それなら朔が気持ち悪く思うのも当然の事だったんだ。
ショックの余り夏生が赤くなったり青くなったりしながら黙り込むと「じょ、冗談だって」と透は慌ててフォローし、それに由紀が口をはさむ。
「田巻は男の癖に目ざといから、たまたま気付いただけよ」
「人の心の機微に繊細と言って欲しいね」
「アホか――で、何かあったわけね?」
冗談の応酬に、夏生の気分も多少は和らいだが、由紀の核心に迫る質問で話題がまた戻された事を知った。四つの瞳が自分のほうを見ている。じっと自分が相談するまで待っているであろう二人を目の前にして、ようやく夏生は観念し重たい口を開いた。
「はぁ? 何それ……超感じ悪いじゃない。あり得ない」
一部始終を聞いた由紀は一気に沸点まで突っ切ったらしく、憤慨しきった様子で朔の態度や言葉に本気で腹を立てている。そうするとおかしな物で、夏生は自分が当事者であるのに、まるで人事のように朔のフォローをするようなことを口にしていた。
「でも、私が睦月君を見ていたのは事実だし……。やっぱりじろじろ見られたらいい気はしないから」
「だからって、わざわざレポートを持ってきた夏生に有難うもなしに、気持ち悪い。だぁ? どこのアイドル様だってのよ」
由紀は腹の虫が納まらないといった感じでイライラと頭をかきむしっていたが「おねーさん、ブルーベリームース追加!」と注文した。怒りでやけ食いするタイプらしい。そんな由紀に反して静かに考え込んでいた透は、いつもと比べてゆっくりと言葉を選びつつ話し始めた。
「俺なら、女の子に見つめられたら逆に嬉しいけどな。あれ、もしかして俺に気がある? とかって普通、期待したりするし。――まぁ、流石に無言でずーっと見られてたら怖ぇけど」
最後の言葉に夏生が少しだけ落ち込みかけると、由紀が正面に座っていた透の向こう脛を机の下で蹴飛ばしたらしく、痛ぇ! と透が叫んだ。
「っつ。田辺さんみたいな可愛い子なら、どんなやつだって大歓迎だと思う」
痛みを堪えながらもそう付け加えたのは明らかに励ますための透のお世辞だったけど、その気持ちが嬉しかったから、夏生は有難うと少しだけ笑った。それに透もほっとしたらしく、脛を摩りながらもいつもの人懐っこい笑顔を浮かべた。
由紀は朔に対してまだ激しく怒っているみたいだったが、夏生の手前もあってか罵るのは心の中にとめていたらしい。ばっくばくと凄い勢いでムースをかきこんでいる。
夏生はそんな二人の顔を交互にみつめて心から感謝の気持ちを伝えた。
「二人に話し聞いてもらったら、かなり楽になった。ほんとにありがとう」
透はそれにむずがゆい様な顔をしていたが、由紀は食べきったムースの皿を遠ざけてから、この話は終わりとばかりに声を張り上げた。
「さぁさ、今日は健気な夏生に免じて、田巻が奢ってくれるってさ!」
「ちょっと待て……なんでそうなるんだよ」
「は? アンタ、傷心の女の子からお金取るっての?」
「私、自分で払うから」
急に透に奢らせると言い出した由紀に夏生は慌てて自分の財布を引っ張り出した。
夏生の斜め前に座っていた透は、にやにやとした由紀の表情を受けて、観念したように深いため息を一つ吐く。そして夏生と視線を合わせると、少しだけ照れ臭そうな表情で夏生の財布をしまうように言った。
「――というわけで田辺さん。ここは一つ、俺に奢らせてくれない?」
「やった! ゴチになりまーす!」
「曽根川、言っとくけどお前の分は払わねぇからな!」
しっかりと釘を刺した透に由紀はケチと口を尖らせていたが、所詮冗談だったらしく、口の端は笑っている。夏生は何の理由も無く奢ってもらう事に抵抗があったから、頑なに断ろうとすると、由紀がふざけた口調で付け加えた。
「夏生。自称フェミニスト、田巻透がここまで言ってるんだからさぁ。男にしてやってよ」
「――お前に言われると、なんだかすげぇ腹立つな」
透を見てみると顔がうっすら紅潮している。由紀から強制されたとは言え、その気障な行動に照れているのだろう。――二人とも自分を励ましてくれているのだ。
それにじんわりと心があったまっていくような気がして、夏生はお気に入りの財布のがま口をパチンと閉じた。
そしてこの日初めての満面の笑顔を浮かべて「ゴチになります」と小さい声で透に頭を下げた。
 
|