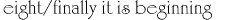
サークルがある二人とは別れ、夏生はどこかふわふわと浮き立つような足取りで家路に付いた。夏生は校門までの並木道をゆったりと進んでいく。ほんのり色づいた樹木達は、衣替えの季節に僅かにそわそわしているようにも見えた。歩みを進めるうちに並木道の中ほどにあるベンチが目に入る。
そこに座っているのは講義室から去ったはずの朔だった。その姿を認めて夏生の緊張は一気に高まったが、今になって避けるのもあからさまだ。夏生はぎゅっと唇を噛み締めた。一歩、二歩、近づいていく距離にぴりぴりとした空気を感じて、夏生の足取りも次第に鈍る。それでもなるべく早く通り過ぎようと夏生は無理に足を速めた。
「待て」
やっと通り過ぎる、と思った所で朔の声。
過剰に反応してしまいそうな自分を抑えて夏生はゆっくりと慎重に視線を移す。鉄製のベンチに座り込んでいた朔は地面を見つめていた顔をゆっくりと上げた。その眼に写るのは苛立ちの混じった――困惑。 何故、彼は怒っているのだろう。その理由が解らなくて、夏生は狼狽した。
「何のつもりだ、アンタ」
「え?」
「俺を庇っただろう」
質問に戸惑っている夏生に、朔も唐突に立ち上がりいらいらと言葉を紡ぐ。
その声に聞き惚れそうになりながらも、夏生は先刻の講義室での事を言われているのかとようやく思い当たった。朔は直ぐに部屋を出て行ったはずなのに、夏生たちの言葉が聞えていたのか。夏生が何と返せばいいのか解らずに言葉に詰まる。庇った、とは思っていなかった。ただ単に朔を傷つける言葉を聞きたくなかっただけなのだから。夏生が何も言えずに、朔を見つめていると、彼は表情を強張らせながら吐き捨てた。
「ああいうのは、止めてくれ」
「何で――?」
その声はいつもの如く冷たく、夏生を拒絶する。しかしそれは突き放すような鋭さをわずかに欠いていて。朔の困惑に揺れる瞳が目に入ったとき、夏生の口は勝手に動き、衝動的に聞き返していた。朔は再び夏生を睨みつけて、その薄い唇で言葉を紡ぐ。その声は静かだったが激しい感情でかすかに震えていた。
「アンタのはただの偽善だろう。根暗な奴を庇っていい気にでもなっていたのか? ――同情されると反吐が出る」
血管がぎゅっと凝縮して、手先が冷たくなる。夏生は知らぬ間に拳を握りしめていた。その言葉はさっきの彼ら以上に夏生を傷つける。たぶん、それは誰でもなく朔の言葉だったから。
それでも夏生が言葉を失わなかったのは、言った本人が自分以上に辛そうな顔をしていたからで、夏生の心臓はそれにリンクしているかのように痛んだ。朔はいびつに歪めた顔を隠すように背中を向ける。
夏生に向けられるのはいつも朔の背中だった。
それはお前には関係ない。という朔の拒絶で、自分と朔の間にある見えない壁をいつも痛烈に感じさせるのだ。そのたびに夏生は言葉を失って身動きが取れなくなってしまう。言いたい事を言えないままで。また同じことを繰り返してしまうのだろうか、と夏生は自問する。痛いのから逃げるのは容易い。だけれど、このまま逃げ出してしまうの? ――嫌だ。夏生は初めて強くそう思った。
「――同情じゃないよ」
ぐっと喉から漏れそうな嗚咽を飲み込んで夏生は朔を睨んだ。今にも涙が零れてしまいそうだったが、朔の前では絶対に泣きたくはなかった。乱れそうになる息を大きく吸い込んで、慎重に言葉を吐き出す。
「私が嫌だったから」
(貴方を傷つける言葉を聴くのが)
「だから、私は私のために言った」
(だから、お願い)
「ただの自己満足なの」
(そんな、辛そうな顔しないで)
表面張力に耐え切れなくなった瞳が涙を解放する。頬を濡らしてしまった雫の存在が憎い。己の弱さを、女々しさを強調しているみたいで。夏生はどうしようもなく悔しくて、それにまた泣いた。
滲んだ水の膜の向こう側の朔が弾かれたように振り向き、その顔をゆがめたのがぼんやりと見えた。しかしそれはいつもの険を含んだものではなくて、どうして言いかわからないといった苦々しい顔。
永遠と思われる沈黙が落ちる。夏生は鼻をすすりながら、ずっと下を向いていた。
そしてふと唐突に頬に触れた布の感触に、夏生は驚き、涙が少し引っ込んだ。
「――拭け、俺が泣かせたみたいで体裁悪い」
ぶっきらぼうな言葉に頭が真っ白になる。朔はハンカチで夏生の頬に触れていたのだ。行き成りの事に夏生が固まっていると、その反応の無さに朔は軽く舌打ちをして手を離そうとする。何故かそれを離したくなくて、夏生は無意識に朔の手へと手を伸ばす。それに朔は珍しく驚いたような表情をして体を引いた。
「……何なんだ」
「あ、御免なさい」
しっかりとハンカチを手で捕まえているくせに、どこか遠慮がちに言った夏生。朔は少しの間、夏生を凝視すると、今度ははっきりと苦笑した。そのぎこちない困ったような笑顔に夏生は息を止める。さっきとは違った意味で心臓が痛くなってしまった。空色のハンカチに涙の名残が滲んでいく。雨模様になったハンカチは微かにアイロンの匂いがした。その持ち主は鋭い眼を伏せて呟く。
「アンタはいつも謝ってばかりだな」
それは朔の前では緊張して失敗ばかりしてしまうからだと言いたかったけれど、その台詞はまるで陳腐な告白のようで夏生は恥ずかしくなって飲み込んだ。
「きつい事言って―――悪かった」
赤い顔を隠すように伏せていた夏生は、その言葉に弾かれたように顔を上げる。朔は決まりの悪そうな顔をしながら、明後日の方向を向いている。夏生は勢いよく首を横に振った。
「私もいろいろ迷惑かけたから――気にしないで」
「そうか」
僅かな変化だけれど、朔がほっとしたのがわかった。雪が溶けるみたいにぴんと張り詰めていた空気が緩む。借りてしまったハンカチを握り締めながら、涙が完璧に引っ込んでしまうと、夏生は今の状況を冷静に意識した。――私、睦月君と喋ってる。
血がかっと一気に上ってくる。いつも冷たくされるのが普通で、こんな風に会話できるような気安い関係ではないのだ。意識すると意識したぶんだけどくどくと脈拍が増した気がする。
――どうしよう。
彼は珍しく怒ってもいないのに何故こんなに緊張してしまうんだろう。どうして心臓がこんなにも痛いのだろう。
「それから――レポート。礼を言い忘れた」
ぐるぐると考えていた夏生の意識を戻したのは、朔のそんな言葉だった。今になって言われたのが不思議で夏生が首をかしげると、朔は唇の端を少しだけ緩めた。そのぎこちない笑顔がとっても優しくて、夏生は魅了される。
「『礼もいえないのか』――アンタに言っといて、自分が出来てなければ、ざま無いからな」
覚えていたんだ、という驚きとともに襲ってきたのは喜びと強い既視感。
あの時、朔は夏生の心をいっそ無遠慮と思えるほどに振るわせたのだ。生温い羊水の中で眠っていた自分はその音を聞き、色を持っていた世界を見た。そしてその美しさに心を奪われた。
耳にした二度目の台詞、しかしその冷たい海は少しだけ柔らかさを纏って、夏生をあの時よりも強くひきつけた。
ぱちん、と軽やかな音を立て何かが破れた。
あのお化けが視界の端を横切った気がして、ふと夏生は顔を上げた。唐突に理解する。
――そうか、これは恋だった。
色づき動き出した世界。
変わったのはなんだったのか。
それは、そう。
終わりで始まり。
- 了 -
 
|